
「やめさっしゃい」と「やめられん」のあいだで
長かった酷暑も落ち着いた10月8日、夜の7時から、きこりプロジェクトの説明・交流会を数年ぶりに開くことができました。感染症流行の下で控えてきたもので、再開できたことがなによりです。地域行事の中には、ここ数年同様の中止を経て再開を諦めたものも少なくないようですので。
ともあれ、横田コミュニティセンターに13名が集まったのでした。 事務局から30分ほどの状況説明の後、会員同士の意見交換。言いにくいことも言える場にしたいということで交流会と名づけ、1時間半あまりそれぞれが思っていることを結論を急ぐことなく出し合いました。その一端をレポートしつつ、意義を見出していこうと思います。
山に入るのはやめさっしゃい
今回のテーマは「山に入ろう」。 枝打ち、除伐・間伐、ツル切り、草刈りといった山林の管理・手入れから、山菜、薪、椎茸の榾木など、山に入ってすること、手に入るものは、山ほどあるものです。
いや、山なんか用がない、金にならない、時間もない―と言われもしますが、何かあるからこそ、人は山に入り続けてきたものです。 それが年々、年をおうごとに減ってきています。なぜでしょう? という問いから場をはじめました。
●熊が出る、出たとこれだけ騒いでいるのに、山に入ろうなんて言っていいのか?
●年に一回はほんにあぶないと思うことがある。帰ってその話をすると、年寄りふたり暮らしだのに、ひとりにするつもりかと言われる。もう、やめさっしゃい、と。
●先祖から継いだものだし、愛着もあるが、いいんじゃないか。よう動かんようになってきたし、みげたら損だ。
―これまで山に入っていた人たちが後期高齢者と呼ばれる年齢に差し掛かっています。 山の世話をしてきた世代がこれから本当に引退していく時期に入るのですね。問題はその後を引き継ぐ人が育っていない、極端に少ないということです。
一方で、やっぱり山は楽しい、おもしろいという言葉もどんどん出てくるのです。

▲10月8日の説明交流会は横田コミュニティセンターで。手前は閲覧用の資料・雑誌や書籍など。伐木方法、メンテナンス等、技術関連の書籍・雑誌は関心が高かったです。
山はやめられん もうけもある
●奥のほうまで道つけて、気持ちよーなる。山がよーなってくるのをみると、やめられん。
●金にはようならんが、雑木山をかまうのがいちばんいい。遊べる。
●雑木木山は金になーわな。ほだ木でもバンバン出してみい。
●山に入るには知恵がいる。頭も体も使えるうちは使うと、元気になる。
――これら、実は「やれん」と言っていた同じ口から出てきます。 その場では特段に不自然ではないのです。文字にすると一義的一面的な意味が表立ち、ニュアンスというような表現のひだが消えてしまいます。
昨今、とかく矛盾、不整合を見つけては排除しようとする風潮がありますが、自然はもちろん社会だって合理性だけで成り立ってはいないのですし、まして「山」との付き合いはなおさらでありましょう。
どうしたら山に入れるようになるか。答えは「やめさっしゃい」と「やめられん」の間にあると、そう考えるのはどうでしょう。
仲間でやれて少し儲けもあって若いもんもおって
話の帰結をそれとなくまとめると、上に掲げた見出しの言葉になります。
山に入れない、入らなくなったのは、「ひとり×年寄り×儲けなし」だからということです。これを逆さまに回転させれば、もとに戻るのでは? 山へ人が次々と戻りはじめるのでは?
「グループでやっていた頃はよかった。張り合いもあった」と、懐しい思い出のように語るそれは、思い出として語るだけの夢にとどめておく手はありません。
ここに、これからの活動の大きなヒントがありそうですね。「少しの儲け」というところに、プロジェクトの間伐材出荷が役に立たないでしょうか。1tで6,000円の商品券です。

▲11月9日のチェーンソー研修では、雑木伐木コースを設けました。山の実践技術の習得は、原理・理論と同様に見様見真似、まずやってみる、というような現場的で属人的なものが不可欠です。かつ、それは面白く楽しい。

▲雑木山から得られる山菜、茸、炭の材などは、大きな市場・流通を使わずともさばけることが特徴です。はじめやすいという点にもつながります。
作業道をつけることから―共同出荷と実践研修と場づくり
今年度は作業道づくりの見学・体験会を実施し、町内外から5名が参加しました。従来の作業道敷設支援事業では、講師の派遣で「道をつけたい」意欲ある個人への対応でした。枠をひろげたのは、ちょっと興味があるだとかそもそも作業道ってどんなものか知りたいという方へ、その有効性と面白さ、奥深さを伝えたいという意図がありました。

▲11/16に八川地区内山林で実施した作業道づくりの見学・体験会
今回の応募サイト「なぜ、今、作業道なのか」でも述べたことですが、かつて作業道といえば、皆伐するために作るもので、あとは使わない=荒れても壊れてもいい道ーという使われ方もしていました。ある意味大事業であって、そんなのとても無理だと思う人がいても不思議ではありません。
プロジェクトでつけている作業道はいわば管理道であって、持続的に山をいいものにしていく、資産価値のある森を育てていくための道です。
山に入って仕事をするためには、ほかにもたくさんの技術を要しますが、その核心たるものが作業道づくりであると、プロジェクトでは捉えているのです。
きこり通信14号でもとりあげましたが、プロジェクトの研修メニューでいちばん応募があるのはチェーンソー研修です。ただ、ほかの研修や講座などとあわせることで、その効果が高まることが、下の図からなんとなくでも感じていただければと思います。

作業道づくりが大切なのは――それによってはじめて自分の山を自分で手入れし、山林所得が得られるようになるということがひとつ。そして、やりがいと誇りと楽しみが生まれるということ。
技術的にも条件的にも容易なことではありません。 そこで、研修や練習、体験を交えながら、共同で行いながら進めていくというやり方。部分的には現に進めているものを少しずつひろげていこうとしています。今冬の実践研修もその一環ですので、ご参加のほどを。
テキストやマニュアルが通用しないのが作業道づくり
当プロジェクトの道づくりは、徳島県の橋本光治さんに何年にもわたり講師として出向いていただき、指導を受けたものです。
道をみたら、どんな人かはすぐわかる。道づくりは人づくりだとも。
道をつけること、仲間で取り組むこと、技能を磨くこと、楽しむこと、少しはもうけること。そんなことがつながる循環へ、まず一歩。そんな一年にしたいものです。

▲上はこの11月につけた作業道の一コマ。こうした樹を伐らないで残す方針です。樹と山を信じるということでもあります。伐られた根は朽ちるものもあれば生きて路肩をおさえ、根づくものもある。下は道をつけて40年が経過したもので徳島の橋本さんの山林の樹。


▲作業道の要諦はルートづけ。ルートが決まれば、ほとんどできたようなものだといわれます。

▲山林見学会で訪れた加食の川の東屋。自治会のグループ活動によるもの。

▲他県の作業道講習で。寒中の暖がとれるのは、グループ活動のよさ。
きこり通信15号 Down load実際に会員に配布されるもののPDF版は上のボタンからダウンロードできます。ご自由にプリントしてもご覧いただけます。

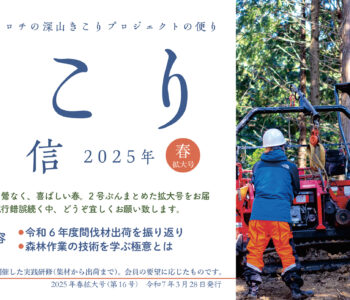





2 COMMENTS
きこり通信を初めてちゃんと読みました🙇山も田んぼも金にならないや、しんどいキツイ仕事という価値判断から人離れを憂う者の一人です。昨年一度だけチェンソー研修で学ばせて頂きました。今年は山の管理の仕方、恵みを学びたいと思います🙋また以前から竹山の整備やビジネス化に興味があります。それもご教示頂けると嬉しいです。山に取組むことで半農半Xの半Xが一つ増えると取組みたいと思います。よろしくお願いします🙇
宝田さま コメントありがとうございます。事務局の面代です。
期待にそえるよう、動いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。